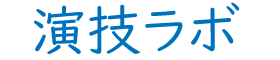身体演技について
目的:身体を取り戻す。
精神の道具とされている身体を取り戻すこと
いくら精神集中して芝居をしても、表現するときには、身体を媒体とします。また、精神活動を助けているものが、脳だとするなら、その脳が所属しているのも身体であるわけです。私たちは、この身体を避けて、表現することは、不可能なわけです。
その不可避な身体について、私たちは、あまりにも無頓着というか人生の道具として身体をとらえ、精神の都合で、いくらでも加工されていく身体は、もはや遠い存在になってしまいました。
ここでは、芝居の表現ということを通じて、身体を自分に取り戻すことをしていきたいと考えております。
少しでもわかりやすくするために
武士のならひのなかにブログを書き始めました。身体演技の研究
概論
あまりにも広範囲でとりとめもない演劇アプローチであるので、おおまかな概論というか、何が問題として取り組んでいるのかを示します。
・身体集中であること
・彼我問題 自分と相手 演者と観客
・内側と外側の問題 台詞は内側なのか外側の問題なのかなど
・局所と全体 役作りは全体性の問題だが、演技は全体性では演じられない
・時間と空間の問題 変化していく時間と空間
身体演技の注意点
ここから、やろうとしていることは、一般常識からは、かけ離れていきますので、注意が必要です。興味本位で、ワークショップに参加することは、とても良いことだと思いますが、いずれ無理と思われることが、あるかもしれませんので、あらかじめ向いていない人を書いておきます。もちろん、個人差がありますし、ここに書かれたから、参加できないとかではないです。
・肩書きや実績を重視されるかた
・現状の自分に自信がある、または、とても上手くいっているかた
・すべて理解したり、納得しないと、試すことが、出来ない人
外論
ワークショップ
・ただ今一月に一度のペースで、着物ドリーマーズのお店でワークショップを行っております
どなた様でも、ご参加いただけます。基本的には、後戻りしない予定です。
だから、最初からワークショップに参加してなければ、駄目だということは、一切ありません。
そうした基礎があって、応用みたいな、学習体系もちょっとそぐわないと、思っております。
ご縁があれば、お目にかかるのを楽しみにしています。